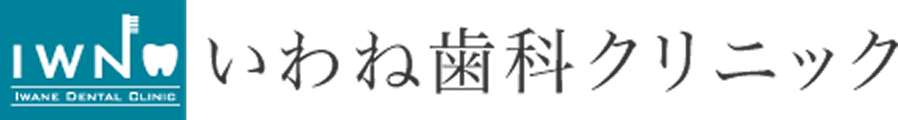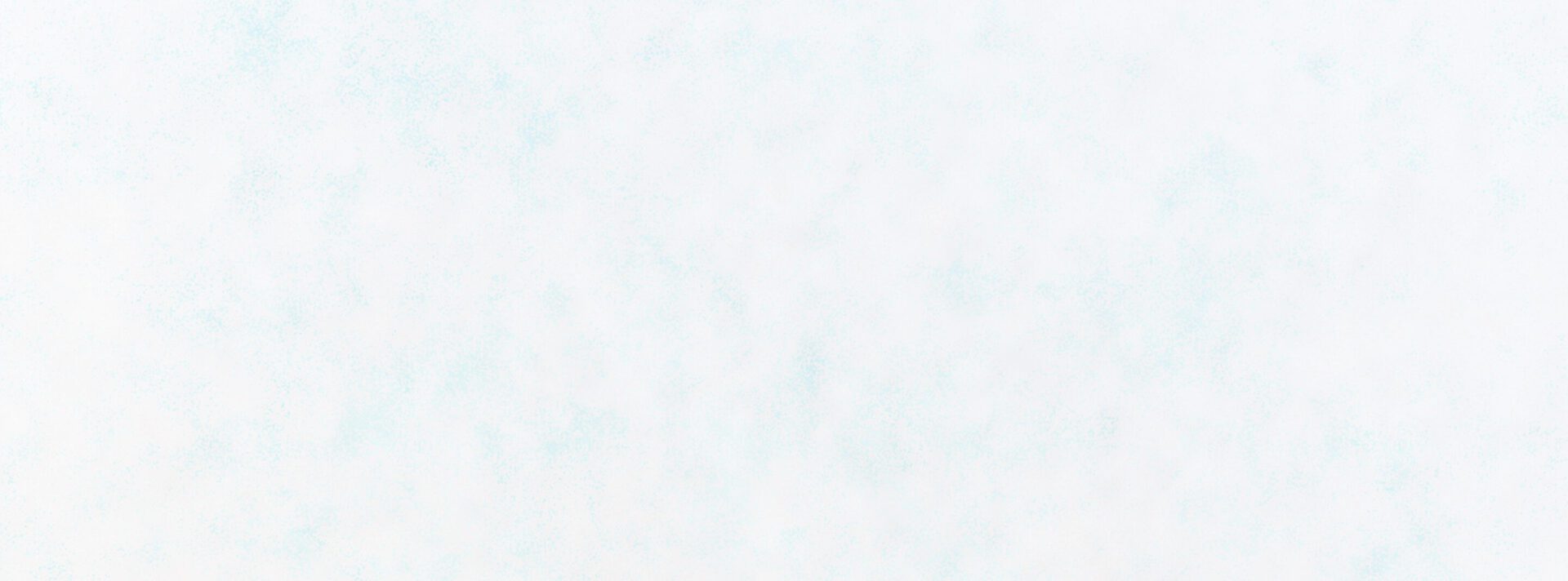
親知らずとは

親知らずは、歯並びの一番奥に生えてくる永久歯で、「智歯(ちし)」とも呼ばれます。多くの場合、20歳前後に生え始めますが、すべての人に生えるわけではありません。
生えるスペースが足りないと、斜めや横向きのまま埋まってしまい(水平埋伏歯:すいへいまいふくちし)、痛みや腫れを引き起こすことがあります。また、親知らずは奥にあるため歯ブラシが届きにくく、むし歯や歯周病のリスクが高くなり、周囲の健康な歯にも悪影響を及ぼすことがあります。
特に、下顎の親知らずが横向きに生えていると、隣の歯を押して歯並びを乱したり、噛み合わせに問題を引き起こしたりすることもあるため、抜歯を検討するケースが少なくありません。
「親知らずの抜歯」と聞くと、不安を感じる方も多いですが、適切な処置を受けることで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
当院の親知らずの治療の特徴
当院では、親知らずの抜歯に対して不安を感じている方にも安心していただける診療体制を整えています。
斜めに生えている、歯ぐきに埋まっている、神経に近いといった難しい症例にも対応可能で、歯科用CTを活用して神経や骨との位置関係を立体的に把握したうえで、安全性の高い処置を行います。
また、術前の丁寧な説明と、痛みや腫れに配慮した麻酔・処置を徹底しており、できるだけ身体への負担を少なくすることを心がけています。術後のケアや注意点についてもわかりやすくご案内し、必要に応じてお薬の処方や経過観察も行っています。
「大学病院でないと抜けないと言われた」「抜くべきか悩んでいる」という方も、まずはお気軽にご相談ください。当院が親知らずの不安を丁寧にサポートいたします。
親知らずは必ず抜く必要がある?

親知らずは、必ずしも抜く必要はありません。しかし、正常に機能していない場合や、将来的なトラブルの原因になりそうな場合は、抜歯を検討することが推奨されます。
例えば、上下の噛み合わせが合っていない親知らずは、実質的に役割を果たしていません。また、レントゲン検査で確認すると、多くの場合真っ直ぐ生えず、横向きや斜めに埋まっているケース(埋伏歯)が見られます。このような親知らずは、歯ブラシが届きにくいため汚れが溜まりやすく、歯茎の炎症や腫れ、さらには膿が溜まることで強い痛みを引き起こすこともあります。現代人の顎は小さくなっており、親知らずの必要性は以前よりも低くなっていると言えるでしょう。
機能していないうえに、口腔内に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、歯科医師から抜歯を提案されることが多くなります。親知らずを抜くべきかどうか迷ったときは、一度歯医者で診察を受け、自分の状態に合った治療方針を確認すると安心です。
近年では再生医療の発展により、親知らずを移植する治療法も登場しています。適応には制限があり、主に奥歯の治療に限られますが、将来的に活用できる可能性がある場合は、あえて抜かずに残しておくという選択肢も考えられます。
また、妊娠している方の場合、親知らずの抜歯は可能であれば避けたいところです。どうしても治療が必要な場合は、安定期に入ってからの処置が望ましいでしょう。局所麻酔は基本的に問題ありませんが、抜歯後の鎮痛剤や抗生物質の使用には細心の注意を払う必要があります。
親知らずによる炎症や痛みを防ぐには、日頃のケアが大切です。歯科衛生士による定期的なクリーニング(歯周治療)を受けることで、歯茎の健康を維持し、歯周病や炎症を未然に防ぐことができます。また、自宅での丁寧な歯磨きも重要です。普段から予防歯科を活用し、むし歯や歯周病のリスクを減らす習慣をつけておきましょう。
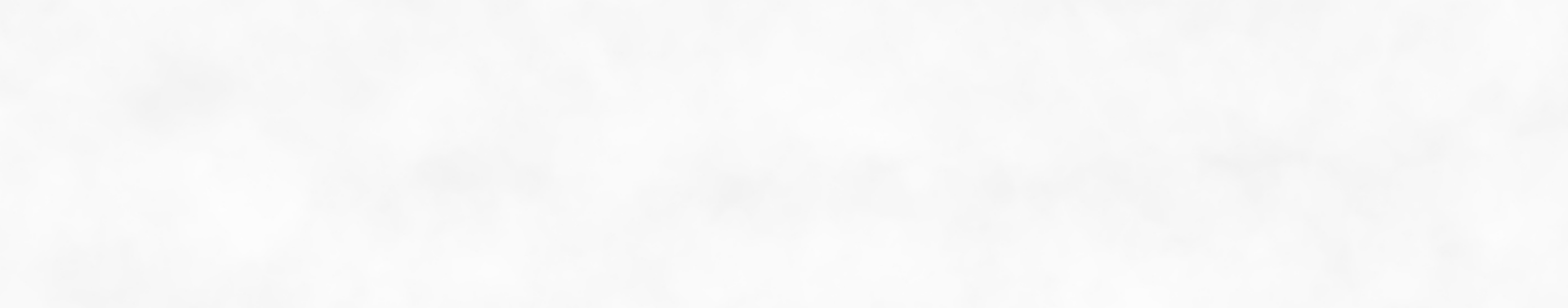
以下のようなお悩みはありませんか?

- 親知らずが上下で噛み合っていない
- 横向きに生えていて汚れが溜まりやすい
- その他、親知らずによる影響が心配
気になることがございましたら、一度当院までご相談ください。
親知らずにむし歯ができた場合
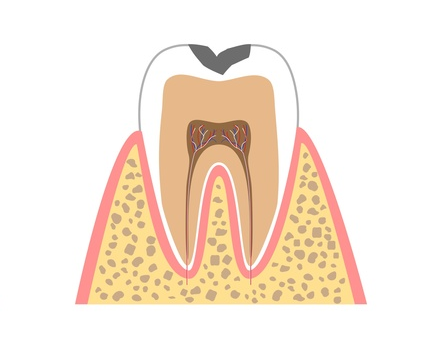
親知らずがむし歯や歯周病にかかると、放置すると繰り返しむし歯が進行するリスクが高くなるため、早期に抜歯を勧められることが多いです。現代人にとって親知らずは必ずしも必要な歯ではなく、噛み合わせが良好に機能することは稀です。歯としての役割を十分に果たさない場合、むし歯になりやすくなるため、抜歯が推奨されることが多いです。しかし、反対側の歯と正常に噛み合っている場合には、むし歯治療として詰め物や根管治療(抜髄治療)を行い、その後歯冠に修復物を被せることで治療することが可能です。
さらに、親知らずはむし歯以外にも、歯周病のリスクも高めます。歯磨きが不十分だと、親知らず周辺に歯周病菌などの細菌が侵入し、炎症を引き起こすことがあります。最初は違和感程度の症状が現れますが、次第に激しい痛みや腫れを伴う智歯周囲炎(ちししゅういえん)に進行することがあります。炎症が悪化すると、歯を支える顎の骨にも影響を与えることがあり、特に上顎で親知らずが膿を伴い、上顎洞に感染が広がると非常に厄介な状況となります。
こうしたむし歯や歯周病の炎症が周囲の組織に広がると、「歯性感染症」という疾患を引き起こすことがあります。歯性感染症では、抗生物質を使用して炎症を抑える治療が行われます。
このように、親知らずの管理は歯周病リスクを軽減するためにも非常に重要です。歯周病は親知らず自体だけでなく、周囲の健康な歯にも悪影響を与える可能性があるため、早期に対処することが大切です。特に、下顎の水平埋伏智歯が神経や太い血管の近くに位置している場合、抜歯後に神経麻痺を引き起こすリスクもあります。そのため、このような場合は、口腔外科の専門医による抜歯が推奨されます。
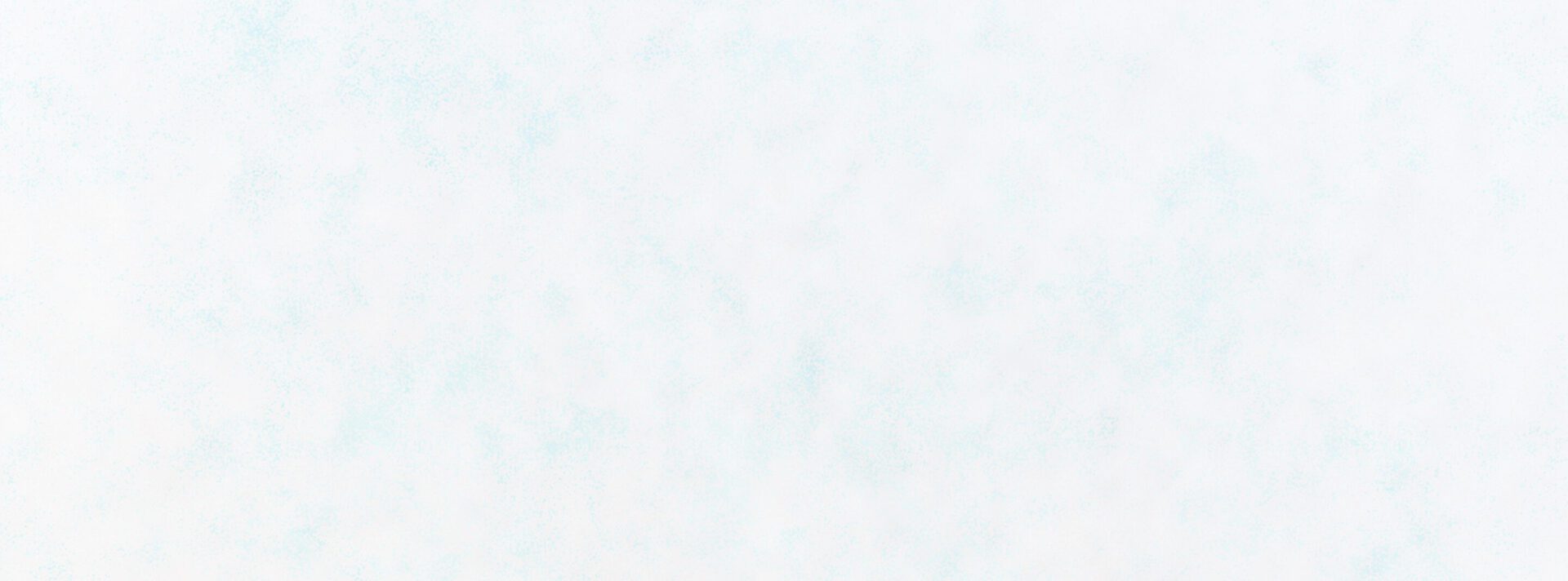
親知らずが原因で頭痛が起こる?

親知らずは、十分なスペースがないため、真っ直ぐに生えてくることは稀です。その結果、斜めに生えてしまうことが多く、周囲の歯を押しながら生えてくることがあります。このような親知らずが生えると、噛み合わせに影響を与え、歯並びが乱れる原因となることがあります。
噛み合わせが崩れると、顎に過度な負担がかかり、顔周りの筋肉のバランスも乱れてしまいます。これが原因で、顎関節症を引き起こしたり、こめかみや頭部に痛みを感じたりすることがあります。急激な痛みを感じた場合は、応急処置として冷やすことや、消炎鎮痛剤(例:ロキソニン)を使用して痛みを抑え、その後、かかりつけの歯医者で痛みの原因を取り除くことをお勧めします。
また、親知らずが生えていることで、歯並びが悪化するリスクについても最近では注目されています。最悪の場合、歯並びだけでなく、顔全体の印象にも影響を与えることがありますので、早期の対応が重要です。
このように、親知らずの問題は痛みだけでなく、見た目にも大きな影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
親知らずの抜歯について
親知らずの抜歯は1日で終わる?
検査を行い、抜歯方法を決定した後、抜歯の日時が決まると、その日のうちに処置を行うことが可能です。抜歯後に縫合が必要な場合は、数日後に抜糸のために再度来院頂くことがあります。
また、傷口の消毒のために翌日再診が必要な場合もありますが、抜歯自体は1回の通院で完了し、何度も通院する必要はありません。
親知らずの抜歯は痛い?
親知らずが正常に生えている場合、抜歯は比較的簡単で、痛みも少なく処置が行えます。しかし、親知らずが横向きに生えていたり、神経を圧迫していたりする場合は、抜歯後に頬の腫れや痛みを引き起こすことがあります。また、噛み合わせていない親知らずや、むし歯でボロボロになっている場合も、早めに抜歯を行うことが推奨されます。風邪などで体調を崩すと、顔や顎が腫れやすくなることがあるため、できるだけ健康な状態で治療を受けることが望ましいです。
抜歯後の注意事項
抜歯後は、飲酒や激しい運動を避けることが重要です。血流が良くなると、抜歯後にできた血餅(けっぺい:血の塊)が外れてしまい、ドライソケットと呼ばれる状態を引き起こすことがあります。これにより、強い痛みが生じることや、出血が止まりにくくなること、腫れがひどくなることがあるため、熱いお風呂も控え、シャワーで済ませましょう。さらに、麻酔を使用することが多いため、食事に支障をきたす場合もあります。辛い食べ物や刺激の強い料理は、痛みやしみる原因になることがあるため注意が必要です。場合によっては、炎症が顎関節に広がり、顎関節症の症状が現れることもあるので、これも気をつけなければなりません。
抜歯後は腫れる?
親知らずがほとんど歯茎に埋まっている場合、歯茎を切開して抜歯を行います。この場合、手術後に腫れが生じることがありますが、通常は1日から3日程度で腫れは引いてきます。
親知らずの生え方など人によって腫れ方は異なりますが、処方されたお薬を医師の指示に従って服用しましょう。
健康保険は適用される?
親知らずに痛みがある場合、その治療は基本的に保険が適用されます。しかし、矯正治療やインプラント治療、美容目的の治療については、保険が適用されずに自費診療の扱いとなることがあるため、事前に確認しておくことが重要です。
抜歯費用は?
親知らずの生え方や検査内容によって料金は変動しましが、一般的に3割負担の場合、3,000~5,000円で抜歯を行えます。
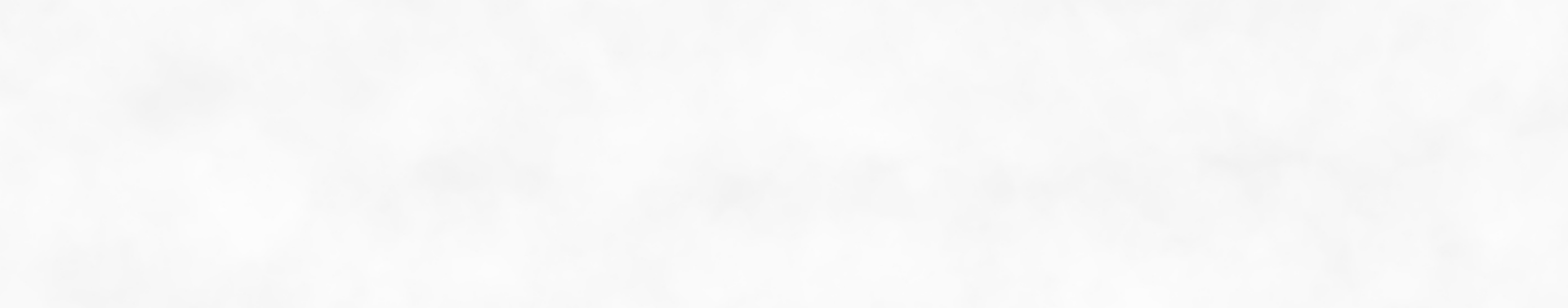
南与野のいわね歯科クリニックの基本情報
いわね歯科クリニック
〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀10丁目11−38
048-753-9045
JR埼京線 南与野駅 徒歩6分